東西組合細見 neo22/大日本土木労働組合

左上から 大石 東京支部執行委員長(兼 賃金対策部長)、戸田 名古屋支部執行委員長(兼 福祉法規対策部長)、荒俣 大阪支部執行委員長(兼 教育宣伝部長) 左下から 伊藤 本部書記長、北川 本部執行委員長、江村 本部副執行委員長、サイドナシモフ 本部副書記長
大日本土木は、1924年に岐阜市で創業、1944年の創立以来、ダムやトンネルなどの土木事業を中心に、公共施設などの建築事業とあわせて手がけてきました。そして今日、手がける事業は多用な広がりを見せ、建築:土木の比率は50%:50%で、海外ODA案件にも積極的に取り組んでおり、2024年で80周年を迎えました。
大日本土木労組は、1951年に大阪地区にて組合前身組織が発足し、続いて岐阜地区と東京地区で設立、その後1966年に3組織が統一され、現在の大日本土木労働組合が誕生しました。2025年度は「Shift in mentality」をスローガンに掲げ、特に若手組合員の成長とコミュニケーションの促進に力を入れており、レクリエーション活動や組合員間の交流促進を目指して活動しています。
なお、東京本社ならびに組合事務所は、都庁や高層ビルそして新宿中央公園に囲まれた新宿区西新宿に所在しています。
| ◆ 設 立:1951年 4月(1966年11月に統合) | ◆ 組合員数::602名(2025年7月現在) |
| ◆ 本部執行委員数:7名 | ◆ 組織率:64% |
| ◆ 支部数:3支部(東京、名古屋、大阪) | ◆ 中央執行委員会:年7回 |
小規模レクでコミュニケーションの活性化

北川本部執行委員長
2024年度から組合員同士の交流の場を提供する目的で、小規模レクリエーションを開催しています。レクリエーション内容については、懇親会や釣り、ゴルフなど多種多様で3名以上または2事業所以上の組合員で気軽に開催できる活動としています。この活動自体は一定の成果を上げていますが、参加率がまだ低いため、2025年度は制度を改定し、さらなる参加者の増加を目指しています。また、レクリエーション活動を通じて、組合員同士のコミュニケーションの活性化やリフレッシュの機会を提供し、働きやすい環境づくりにも寄与しています。
勤怠管理の意識向上にむけて
時間外労働の上限規制が適用されて1年が経過しますが、働き方や作業所の4週8閉所、時短にむけて、日建協の各種アンケート結果をもとに会社との委員会や懇談の場で意見表明を行っています。また、会社での取り組みとして、外勤者の労働時間を業務改善部が主体となり一体的に把握することで、社員や組合員に対して勤怠管理の意識を向上させています。
組合活動の広報に注力
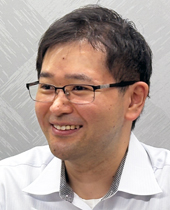
伊藤本部書記長
組合員にむけた活動の広報については、主に年6回程度発行している機関紙や職場会・オルグを通して情報を伝達しています。なお、組合専用のホームページがないため、会社のポータルサイトを利用して情報を伝達していますが、未だ組合員へ情報が行き届いていないことが時折あります。そのため、2025年度は機関紙の内容を含め組合活動に関する内容の充実を図り、労働組合の存在意義などの理解を促進するためにも広報に注力していく予定です。
若手組合員の結束力を向上させるために
コロナ禍の影響もあり組合員間交流・人と人の交流が減少したことに加え、世代間ギャップの大きい人員構成となっており、交流する機会や会話する機会が以前にも増して減少しているように思います。これらは「中間層が極端に少ない=技術継承がままならない」に繋がり、働く環境の改善、賃金改善などと同じくして重要な課題であると感じています。これらの課題を克服するためには、「若手組合員の成長なくして会社の成長は見込めない」という考えのもと、結束力の向上にむけて若手組合員を対象とした交流会を各支部で開催しています。支部全体では、ボウリング大会なども開催していますが、この若手組合員交流会では、バーベキューやビアガーデンでの開催が多く、若手の交流機会が多く作れるようにしています。また、組合員間のコミュニケーションを積極的に取ってもらうために、レクリエーション費用の拡充も行いました。2025年度のスローガンでもある「Shift in mentality」は、これらの意義を込めたものであり、若手組合員の成長と結束力の向上が、組合全体の活力となり、会社の発展にも寄与すると期待しています。

今回の取材では、中間層の組合員が極端に少ない中で、若手組合員の成長とコミュニケーション向上にむけて、レクリエーションや交流会の機会を多く設けるなど、執行部から組合活動を盛り立てていこうとする熱意がよく伝わりました。取材にご協力いただきました北川本部執行委員長、伊藤本部書記長、ありがとうございました。
