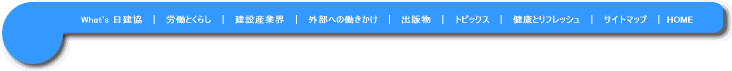
取材協力/松井病院 食養内科部長 長岡由憲先生
わたしたちの生活・仕事・生きることの基本となる「からだの健康」は、すべてに優先される問題です。いつの時代でも健康はすべてに優先される問題です。
「食養」とは食養生のことであり、食事で体を健康にすることです。身体をつくるのはずばり、食事です。健康の維持、回復のためには何を食べるか、またいかに食べるかということを、日本で唯一食養内科を開設している松井病院食養内科部長・長岡先生にお聞きました。
(インタビューは1995年9月に行われた内容です)
レシピ付
料理の写真をクリックすると
レシピが出ます
食養内科とは身体をパーツに分けず、
全体として治療すること
西洋医学では、循環器や消化器というように、身体を部分部分に分けて症状の出た部分を治療します。食養内科では、身体全体のバランスの崩れでどこかに症状が出ると考え、その崩れを漢方屋食事で全体的に整えていくという考え方です。つまり、身体の部分を分けないで、病気・症状の出る原因となる日常生活全般―衣・職・住―に着目し、とりわけ自分でコントロールできる食事に重点をおいた療法を行うわけです。本来、健康は医者ではなく自分で守るべきものですから、基本となる食事はとても大切なのです。
食養は、いわゆる慢性病に効果があります。とくにこのごろはアトピー性皮膚炎が多いですね。他の皮膚疾患、リューマチ、自律神経失調症、高血圧・低血圧症、糖尿病、下痢・便秘症、肥満、腎炎、あとは冷え性や更年期障害などのように検査値には出ないが症状はあるというような、機能低下による症状に食養・漢方が効きます。
治療のポイントは砂糖、油、肉類、白いもの
それらの摂りすぎを避け、野菜、小魚、海藻、ご飯を食べること
症状があるのに、どの病院にいっても検査に引っかからず、気のせいだなどと言われている人は食事療法をやってみる価値があります。本人が自ら治したいと本気になっていることが重要です。食事療法は自分でやるものだしいくらでもサボれますから、本人の意思が重要なのです。
最近とくに多いのがアトピー性皮膚炎ですが、ダニや埃よりも、むしろ食べ物に原因となる要素が多くあります。砂糖と油の摂りすぎは最も懸念されますから、清涼飲料水を飲みながらスナック菓子を食べるなどもってのほかです。そこを正さないからきちんと治らないのです。
具体的には白砂糖、白米、精白小麦粉のパンなど精白したものや、果物、油をできるだけ避けます。牛乳はアレルギーのもとですし、肉類の過食は日本人の消化器構造には向きません。欧米の自然環境や土壌に適した食生活を、戦後の日本人は鵜呑みにしてしまったのです。それよりも、ビタミン・ミネラルが豊富な緑黄色野菜、小魚、海藻といった、日本人が昔からよく食べていたものを積極的に食べるように指導します。
それと、1日に最低2食はご飯、つまりお米を食べて欲しいですね。玄米が理想ですが、五分搗きや胚芽米ならほとんど白米と変わらずに食べられます。ただ、食養でも極端に偏る指導は危険です。生野菜だけを食べるとか、玄米とごま塩だけの食事にするとか・・・。
食事療法で注意していることは、量的にわかりやすく伝えることです。栄養学ではタンパク質などの栄養素やカロリーの数値で考えますが、タンパク質を何グラムといわれてもすぐにわからない。それより小松菜をひとつかみとか、パンと牛乳よりご飯と味噌汁を多くしなさいと言ったほうがわかりやすいでしょう。つまり、食事的なことで指導する「食事学」というような内容の指導が必要だと思っています。
「健康食」と健康食品」は違う
それだけを食べれば健康になれるというものはない
健康食品というのはたとえばローヤルゼリー、プロポリス、プルーン、クロレラなどたくさんありますが、体質に合わなくて皮膚疾患の出た人もいました。これを食べてさえいれば他のものは不必要という考え方は大変危険です。そんな食べ物はあり得ないからです。今はタンパク質が過剰で、ビタミン、ミネラル、食物繊維が慢性的に不足していますので、そういう意味での健康食品は摂ってもよいでしょうが、自分の体質に合ったものを選ばないとお金を捨てることにもなりかねません。
健康食というのは、栄養的にバランスのとれた食事を過不足なく食べることです。野菜や海藻のような身体を調整する食べ物は、1度に多く食べるのではなく、適量を毎日食べつづけることが大事ですね。
砂糖をは身体に不必要な糖
海藻類は毎日食卓に
これまで言ってきたことはすべて病人用と言うことではなくて、健康を保つためにすべての人に共通することです。
ご飯は玄米、五分搗き米、胚芽米のどれかがよいでしょう。味噌汁、緑黄色野菜、魚、海藻、小魚は十分食べて欲しい食品です。白砂糖と油脂はできるだけ控えることです。野菜というとすぐ油炒めですが、煮る・蒸す・茹でるなどして食べるのが理想です。緑黄食野菜にはすばらしい抗酸化作用があります。身体が酸化するのを防いでくれるんです。たとえばカロチンは油によって効能が上がるといわれますが、油でわざわざ炒めなくても食物の中にいくらでも含まれているのですから、カロチンもちゃんと吸収できますよ。
大豆は醗酵すると体内にとても吸収されやすくなりますから、味噌、醤油、納豆は日本人の体質にとても合っているのです。人間は大昔からいろんな菌の助けを借りて生きてきてるんです。こういった基本調味料はできるだけ質の高いものを、できれば無農薬
有機、無添加の自然のものが望ましいですね。
小松菜、ニンジンのジュースもよいでしょう。花粉症なども軽くなります。そして先ほども言いましたが、ワカメ、ひじき、昆布などの海藻を毎日少量でいいですから必ず一品、食卓に乗せるようにして欲しいですね。こういった食事でタンパク質もカルシウムもちゃんと摂れるのです。
それからもうひとつ、砂糖は体内に入るとカルシウムやミネラルを持って逃げますから、身体には必要のない糖だと思ってください。病院での食事療法でも砂糖は使ってませんから。
「健康と食生活」を考える上で
現代人に言いたいことは・・・・・?
食養内科を始めた日野が作った食養法の20か条があって、これを守ることによって健康度が上がり、さらには症状の好転治癒が期待できます。ぜひ試してみてください。しょせん、自分の健康は自分で管理し、守るべきものです。そのための食養であると私は考えています。
食養20か条
1 食品添加物に注意 2 農薬に注意 3 合成洗剤の使用は慎重に 4 精製度の高い(精白した)食品に注意 5 動物タンパクのみを尊重しない 6 緑黄色野菜の摂取に努める 7 海藻を常食する 8 油脂の過剰摂取に注意 9 ビタミン、ミネラルをバランスよく 10 できるだけその土地でとれた旬の新鮮なものを食べる 11 野菜の根も皮も葉も、魚の皮も内臓も食べ、全体食を心がける 12 アクの強いもの以外は、煮こぼしたり茹でこぼしたりは控え、
米とぎも程々に13 生がいいとか、長時間加熱がいいとかにとらわれない 14 塩分や水分の摂取量も、一つの流派の教えにとらわれない 15 合成調味料はできるだけ使わない 16 過熱、過冷、過刺激のものは控えめに 17 清涼飲料水、インスタント、缶詰の使用は慎重に 18 空腹ではないのに食べない。就寝前2時間は飲食を避ける 19 よく噛み味わって食べる 20 食事中、またその前後に湯茶を多量に飲まない
日本は今、世界中の食べ物を味わうことができます。とくに若い世代に激辛好きやマヨラーが増加しています。一概に悪いと決め付けることはできませんが、極端な偏りは避けたほうが無難と言えるでしょう。
健康であればこそ実りある活動ができ、各人の持っている能力が充分に発揮できるものです。自分自身や家族のためにも、専門分野の指導のもとでの、トータルな健康管理の必要性を感じます。■
ページトップへ